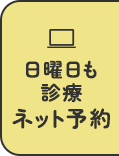巻き爪とは
巻き爪とは、爪の両端が内側に曲がり込み、周囲の皮膚に食い込んでしまう状態のことを指します。初期は軽い違和感程度でも、進行すると強い痛みや炎症、さらには感染を引き起こすことがあり、日常生活にも影響を及ぼします。そのため、早めの対処が大切です。
巻き爪の主な症状には、以下のようなものがあります。
- 爪の変形:通常よりも爪が内側に湾曲し、皮膚に接触する状態になります。
- 痛み:爪が皮膚に食い込むことで炎症や腫れが生じ、強い痛みを伴うことがあります。軽度の場合は痛みを感じにくいこともあります。
- 炎症や感染:巻き込まれた皮膚が赤く腫れ、悪化すると膿がたまることもあります。 症状が進行する前に、適切なケアや治療を行うことが大切です。
陥入爪(かんにゅうそう)とは
爪の端が周囲の皮膚に深く食い込んでしまい、炎症や痛みを引き起こす状態を指します。特に足の親指に多く見られ、症状が進行すると化膿や感染を伴うことがあります。
軽度の巻き爪が徐々に進行して爪が皮膚に食い込み、結果として陥入爪へと発展することがあります。炎症が悪化すると細菌感染を引き起こし、皮膚が化膿するリスクがありますので、早めの治療することが大切です。
巻き爪の原因
巻き爪の原因には、爪の切り方や靴の選び方、歩き方の癖、さらには遺伝的な要因が関係しています。例えば、爪を深く切りすぎたり、角を丸くカットすると、伸びる際に皮膚へ食い込みやすくなり、巻き爪のリスクが高まります。また、先の細い靴や窮屈な靴を履き続けると、爪に強い圧力がかかり、変形しやすくなります。
歩き方や姿勢の影響も大きく、足に偏った負担がかかることで、爪が正常な形を保てなくなることがあります。特に、外反母趾や扁平足といった足の変形があると、爪にかかる圧力が不均衡になり、巻き爪を引き起こしやすくなります。さらに、家族に巻き爪の人が多い場合、体質的に巻き爪になりやすい傾向があります。
このように、日常の習慣や足の特徴が巻き爪の発生に関わっているため、爪の切り方に注意し、無理のない靴を選ぶことが予防につながります。
巻き爪の治療
当院で行うフェノール法は、巻き爪や陥入爪の根治的治療法の一つで、爪が再び食い込むのを防ぐために爪母(爪の生成を担う部分)を処理する方法です。この方法は、特に再発リスクを抑えたい患者さんに適しています。
フェノール法は短時間で完了し、痛みが少ないのが特徴です。外来で受けられ、入院は不要です。
【手術の手順】
- 局所麻酔を施し、痛みを感じない状態にします。
- 患部の血流を一時的に遮断して出血を抑えます。
- 巻き込んでいる部分の爪を切除し、爪母を露出させます。
- フェノール液を爪母に塗布し、爪が特定の箇所から再び生えないように処理します(約5分間)。
- 血流を戻し、傷口を確認した後にガーゼで保護します。
医療機関以外での巻き爪矯正のデメリット
医療機関ではない施設で巻き爪の矯正を受ける際には、いくつかのリスクや制限があります。
- 医療処置ができない
医療機関ではないため、炎症や化膿を伴う巻き爪には対応できません。必要な処置や投薬が行えず、症状が悪化する可能性があります。 - 矯正方法が限定される
一般的にプレート法やワイヤー矯正が用いられますが、矯正力が弱いため治療回数が多くなる傾向があります。重度の巻き爪には対応できないこともあります。 - 再発しやすい
根本的な原因(歩行のクセや足の変形)を改善しないため、矯正後も再発するリスクが高くなります。医療機関での診断と適切な治療が推奨されます。 - 費用がかさむ可能性
1回の施術費用は安価な場合もありますが、通院回数が増えることで長期的には高額になることがあります。また、根治治療ではないため、再発後に再び費用がかかる可能性があります。 - 専門性にばらつきがある
「専門院」と称する施設もありますが、医学的な専門資格がなく、施術者の技術や知識に差があることが問題視されています。 - トラブル時の対応が不十分
矯正後に痛みや炎症が生じた場合、適切な医療対応が受けられないため、症状が悪化するリスクがあります。特に糖尿病などの基礎疾患がある場合は、細菌感染のリスクが高まり注意が必要です。
巻き爪矯正を行う際は、医療機関での診察を受けた上で、適切な治療方法を選ぶことが重要です。特に、炎症や痛みがある場合は、医療機関での専門的な治療を受けることを強くおすすめします。
巻き爪の予防方法
巻き爪を未然に防ぐためには、日頃からの適切なケアと生活習慣が重要です。
- 正しい爪の切り方
爪はスクエアカット(四角形に切る方法)を心掛け、爪の端を丸くカットしないようにします。爪の長さは皮膚の高さと同じかやや長めに調整しましょう。 - 適切な靴の選び方
つま先に適度な余裕がある靴を選び、サイズが合っていない靴の使用は避けます。また、靴が足にしっかりフィットするように調整することも重要です。 - 日常的な歩行
足への適度な負荷が爪の健康維持に役立ちます。歩く際には足全体に重心を乗せ、正しい姿勢で歩きましょう。 - 爪と足の保湿
乾燥は爪を硬く脆くするため、日頃から保湿クリームを使って爪と皮膚をケアすることが大切です。 - 足のトラブルの治療
外反母趾や扁平足などの足の異常がある場合、早めに治療を受けることで巻き爪のリスクを軽減できます。 - ネイルの管理
巻き爪の兆候がある場合、ネイルアートや過度なマニキュアの使用を控え、爪に負担をかけないように注意しましょう。
巻き爪は放置すると痛みや感染症の原因となり、重症化する恐れがあります。軽度の段階であれば、爪の切り方や靴選びの見直しで症状を改善できることもありますが、進行した場合はフェノール法などの専門的な治療が必要です。症状が改善しない場合は、早めに専門医を受診し、適切な治療を受けるようにしましょう。予防と適切なケアを組み合わせることで、巻き爪による生活への影響を最小限に抑えることができます。
魚の目(鶏眼)
魚の目(うおのめ)は、皮膚の特定の部位に 圧力や摩擦が繰り返し加わる ことでできる 角質の厚い塊 です。医学的には「鶏眼(けいがん)」と呼ばれます。足の裏や指にできることが多く、この芯が皮膚に食い込むと、 歩行時に強い痛み を感じることがあります。
魚の目とタコは似ていますが、 魚の目は芯を除去しないと治りにくい という点が異なります。痛みが強い場合や何度も再発する場合は、なるべく早めにご相談ください。
魚の目の特徴と症状
- 硬く厚い角質の中心に芯がある
魚の目の最大の特徴は、中央に「芯」があることです。この芯が皮膚の奥へと食い込むことで 強い痛み を引き起こします。 - 主に足の裏や指にできる
特に 靴が当たる部分や圧力がかかる場所(足の指の付け根、足の小指の側面、親指の付け根など)にできやすいです。 - 痛みがある
軽いものでは痛みを感じないこともありますが、芯が深くなると 歩行時に針を刺されたような鋭い痛み を感じることがあります。
魚の目とタコの違い
| 魚の目(鶏眼) | タコ(胼胝:べんち) | |
| 芯の有無 | あり(痛みを伴うことが多い) | なし(痛みは少ない) |
| 発生原因 | 圧力が局所的にかかる | 圧力が広範囲にかかる |
| できやすい部位 | 足の指や足裏の特定のポイント | 足裏の広い範囲、手のひら |
| 痛みの特徴 | 芯が皮膚に食い込むため痛みが強い | 角質が厚くなるが痛みは少ない |
魚の目の原因
魚の目は 圧力や摩擦が繰り返し加わる ことで発生します。具体的な原因としては
- 合わない靴の使用
サイズが小さい靴やハイヒールは、指や足の特定の部分に負担が集中するため魚の目になりやすいです。一方で、緩すぎる靴も、足が靴の中で動き、摩擦が増えてしまいます。 - 歩き方のクセ
偏った歩き方(外側や内側に重心が偏る)があると、一部の部位に負担がかかるため、発症リスクが高まります。 - 長時間の立ち仕事や歩行
一定の部位に繰り返し圧力がかかるため、角質が厚くなりやすいです。 - 足の変形や骨格の問題
外反母趾や扁平足 の人は、足の特定の部分に負担がかかりやすく、魚の目ができやすいと考えられます。
魚の目の治療法
魚の目は自然に消えることは少なく、芯を取り除かない限り 痛みが続くことがあります。 魚の目の治療法の一つに「削る方法」があります。当院では、メスやハサミを使って角質を削ることで、痛みを軽減します。この処置は、1ヶ月に1回程度の頻度で行うことが推奨されています。
削る際の注意点
魚の目を削る際にはいくつかの注意点があります。まず、芯までしっかり除去しないと再発しやすいため、表面だけを削るのではなく、芯を取り除くことが重要です。また、削る際には感染を防ぐために十分な消毒を行う必要があります。深い魚の目や何度も再発を繰り返す場合は、なるべく早めに受診し、一度診察を受けることをおすすめします。
魚の目の予防法
魚の目は 適切なケア で予防することができます。
- 自分の足に合った靴を選ぶ
・窮屈な靴や、サイズが合わない靴を避ける。
・インソールを使用して足の負担を軽減する。 - 歩き方を見直す
・偏った歩き方になっていないか確認し、必要なら姿勢矯正やインソールで調整する。 - 足の保湿をする
・乾燥した皮膚は硬くなりやすいので、保湿クリーム を使って柔軟性を保つ。 - 長時間の立ち仕事の際はクッション性のある靴を履く
・足にかかる圧力を分散し、負担を減らす。